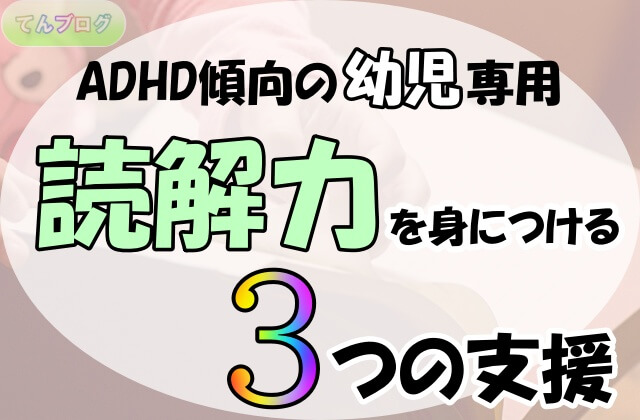うちの子はADHDです。
ADHD傾向です。
幼児です。
- 幼児の頃から読解力は身につけたほうがいいのかな…。
- まわりの子よりも絵本を読んでもあまり内容や意味をわかってない気がする…。
- 小学生になってから困らないように今から子どもに読解力を身につけさせる方法が知りたい…。
今回はこのような悩みを解決します。
子どもが絵本を読んでも内容をわかってないことや絵本の感想を聞いてもあまり話さなかったりすることがよくあって、
「どうしたらいいの…。」
「このままでいいのかしら…。」

と悩んで困ることってありますよね。
そこで今回は、ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられる3つの支援方法について紹介します。
さっそく知りたい方はこちら。
今回の記事を読むことで、
- ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになります。
さらに、自分からいろいろな絵本を読んだり絵本の感想を楽しそうに話したりする子どもの姿を見ることで、今までのあなたの悩みやストレスがパッとなくなります。
保存版
【悩み解決】ADHDの子どもの「育て方の悩み」をまとめて解決したい方はこちら。
本記事の執筆者情報
私は子どもにかかわる仕事を10年以上経験してきました。
- 元小学校教師(通常学級担任、特別支援学級担任をそれぞれ2年以上経験)
- 元障害児通所支援事業所勤務(放課後等デイサービスで、未就学児から小学生までの発達障害の子どもの支援業務を2年以上経験)
- 心理大学卒業のメンタルケア心理士(心理士資格取得のためにADHDの診断基準であるDSM-5を精神医科学基礎で学習。試験では満点。)
この経験を通して、たくさんの保護者に会いました。
子どもが絵本の内容を理解しないことに心配する保護者
子どもが伝えたことに対してあまり理解できていないことに悩む保護者
小学生になるまでにもっと読解力を身につけさせたいと思う保護者
そして、そのようなお母さんから、
「子どもの読解力がまわりの子よりもないことが気になります。どうしたらいいですか?」

と相談を受けて、その子の個性や特徴を考えながらアドバイスをしてきました。
今回の支援方法は、ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけさせるためにはどうやって支援したらいいのか考えて、なやむお母さんにアドバイスして、すぐにつかえて効果のあった方法を紹介します。
3歳から始めた息子の成長を教えます!
必読
最近は子どもが小学生になるまえから習い事を利用する保護者がふえています。「こどもちゃれんじ」の利用を考えているあなたは失敗や後悔をしないようにこちらの記事を今すぐ見てください!
目次
ADHD傾向の幼児に読解力を身につけさせることのたいせつさ
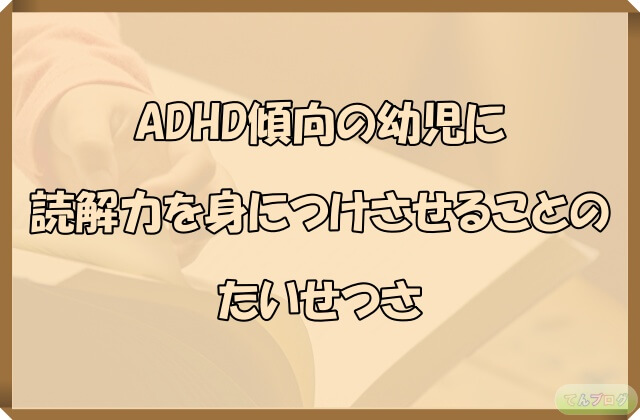
ADHD傾向の幼児にとって読解力は子どもが小学生になったときの「勉強のため」だけではなく、子どもの生活にとって大きな影響を与えます。

読解力の必要性
- 小学生になったときの学習がスムーズになる。
- 問題文を理解する力になるのですべての教科の土台になる。
- 文章の理解力があれば学習への抵抗が減る。
- 自分の考えを言葉で伝えられるようになる。
- 指示を正しく理解できて行動できるので集団行動がスムーズになる。
- 本を読む楽しさがわかるので読書習慣が身につきやすい。
- 本の登場人物の気持ちを考えることで共感力が育つ。
- 自分の気持ちを言葉で表現できるようになる。
- トラブルが起きたときに言葉で解決しやすくなる。
- etc.
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられる3つの支援方法
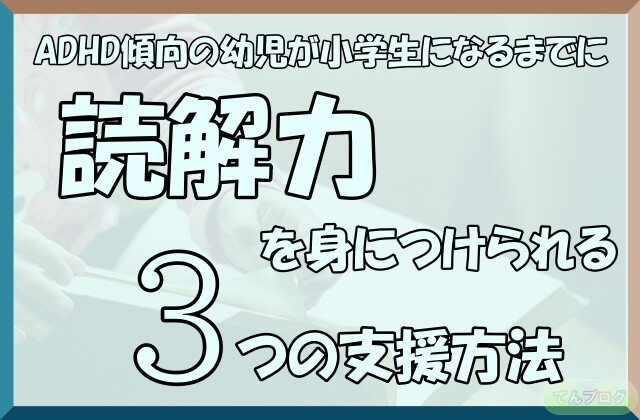
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられる3つの支援方法がこちらです。
内容を理解できるようにする
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになるためには、子どもが読んだ本の内容を理解できるようにすることがたいせつです。
読解力はとっても大切な力です。子どもが将来、国語の学習をするときに役立ちます。
絵本を読んであげてもただ聞き流しているだけだったり、絵本をの挿絵を楽しそうに見ているだけだったりすることで、結局、どんな話だったかわからないADHD傾向の子どもはよくいます。
「はい。」

けれども、絵本の内容を具体的に理解することが難しいことも幼児の特徴です。そのため、幼児の段階では大まかなあらすじだけでも子どもが絵本の内容を理解できていれば子どもの読解力を伸ばせます。そして、小学生に子どもがなったときにこまらないきっかけになります。
テクニック
今からできる子どもの読解力を上げる支援方法は、読んだ絵本の話を子どもとしたり感想を聞いたりするようにしましょう。読んだ本の内容をクイズにしたり一緒に劇などで再現したりすることもおすすめです。
登場人物の気持ちを考えられるようにする
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになるためには、子どもが読んだ絵本の登場人物の気持ちを考えられるようにすることがたいせつです。
絵本に出てくる登場人物がどんな気持ちなのかをセリフや行動、描写などから登場人物の気持ちが考えられるようになれば、それだけで子どもが絵本を読むことの楽しさに気付くことができます。そして、読解力につながります。
子どもがしっかりと登場人物の気持ちを考えたり自分だったらどんな気持ちになるのか考えたりすることで、子どもが登場人物の気持ちを考えられるようになります。
テクニック
読んだ絵本と同じような場面が生活の中であったときに、絵本を持ってきて子どもに絵本のことを思い出させながら「○○ちゃん(登場人物)はこんなことを考えたんだね。」と伝えて登場人物の気持ちを考えさせましょう。
指示語の内容を理解できるようにする
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになるためには、読んだ絵本に出てくる指示語の内容を理解できるようにすることがたいせつです。
- これ
- あれ
- それ
などの指示語が絵本の文章にもよく出てきます。
指示語を子どもがわかれば子どもの読解力をのばすことができます。指示語が何を指しているのかについて文章を読んだときに子どもが理解できないことはよくあります。文章の指示語だけではなく日常生活でも指示語を理解できない場面はよくあると思います。
「はい。」

小学生の国語の学習では指示語がよくでます。そして、テストでも指示語の指していることについて問題になることがよくあります。このようなときに、指示語が指している内容を理解できているかどうかは子どもの読解力の大きな差につながります。
そのため、日頃から、
- これ
- あれ
- それ
などの言葉を使って子どもに何かを伝えるときには指示語が何を意味しているのか子どもに教えてあげるように意識しましょう。
特にADHD傾向の子どもは指示語を理解することが苦手なので今のうちからしっかりと支援してあげましょう。
テクニック
絵本を読み終わったあとに指示語が出てきた文章のところだけをもう1度読み返して、指示語の内容を子どもに理解させるようにしましょう。
まとめ:3つの方法を実践することで、ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになる
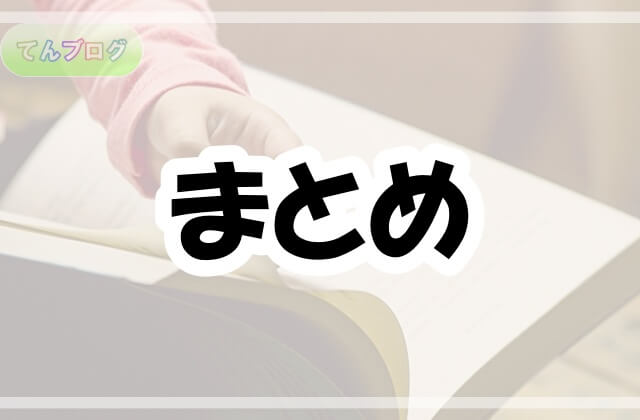
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになるためには、まず、ADHD傾向の幼児に読解力を身につけさせることのたいせつさを知りましょう。
ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられる3つの支援方法がこちらです。
この3つの方法を意識して実践することで、ADHD傾向の幼児が小学生になるまでに読解力を身につけられるようになります。
さらに、自分からいろいろな絵本を読んだり絵本の感想を楽しそうに話したりする子どもの姿を見ることで、今までのあなたの悩みやストレスがパッとなくなり、日々のストレスがスーッと軽くなります。
いつも悩んで、いつも頑張っているあなたの少しでも役に立つ情報になったのなら嬉しいです。ありがとうございました。
子どもに合っていますか?
子どもは放課後等デイサービスや児童発達支援を利用していますか?利用しているならば、子どもに合った放課後等デイサービス(児童発達支援)ですか?ADHDの子どもに合った放課後等デイサービス(児童発達支援)には選び方があります。選び方が気になった方はこちらの記事を見てください。